わたくしは殆ど活動写真を見に行ったことがない。
おぼろ気な記憶をたどれば、明治三十年頃でもあろう。神田錦町(にしきちょう)に在った貸席錦輝館で、サンフランシスコ市街の光景を写したものを見たことがあった。活動写真という言葉のできたのも恐らくはその時分からであろう。それから四十余年を過ぎた今日(こんにち)では、活動という語(ことば)は既にすたれて他のものに代(かえ)られているらしいが、初めて耳にしたものの方が口馴れて言いやすいから、わたくしは依然としてむかしの廃語をここに用いる。
震災の後(のち)、わたくしの家に遊びに来た青年作家の一人が、時勢におくれるからと言って、無理やりにわたくしを赤坂溜池(ためいけ)の活動小屋に連れて行ったことがある。何でも其(その)頃非常に評判の好いものであったというが、見ればモオパッサンの短篇小説を脚色したものであったので、わたくしはあれなら写真を看るにも及ばない。原作をよめばいい。その方がもっと面白いと言ったことがあった。
然し活動写真は老弱(ろうにゃく)の別(わかち)なく、今の人の喜んでこれを見て、日常の話柄(わへい)にしているものであるから、せめてわたくしも、人が何の話をしているのかと云うくらいの事は分るようにして置きたいと思って、活動小屋の前を通りかかる時には看板の画と名題とには勉(つと)めて目を向けるように心がけている。看板を一瞥(べつ)すれば写真を見ずとも脚色の梗概も想像がつくし、どういう場面が喜ばれているかと云う事も会得せられる。
活動写真の看板を一度に最(もっとも)多く一瞥する事のできるのは浅草公園である。ここへ来ればあらゆる種類のものを一ト目に眺めて、おのずから其巧拙をも比較することができる。わたくしは下谷(したや)浅草の方面へ出掛ける時には必ず思出して公園に入り杖(つえ)を池の縁(ふち)に曳(ひ)く。
夕風も追々寒くなくなって来た或日のことである。一軒々々入口の看板を見尽して公園のはずれから千束町(せんぞくまち)へ出たので。右の方は言問橋(ことといばし)左の方は入谷町(いりやまち)、いずれの方へ行こうかと思案しながら歩いて行くと、四十前後の古洋服を着た男がいきなり横合から現れ出て、
「檀那(だんな)、御紹介しましょう。いかがです。」と言う。
「イヤありがとう。」と云って、わたくしは少し歩調を早めると、
「絶好のチャンスですぜ。猟奇的ですぜ。檀那。」と云って尾(つ)いて来る。
「いらない。吉原へ行くんだ。」
ぽん引(びき)と云うのか、源氏というのかよく知らぬが、とにかく怪し気な勧誘者を追払うために、わたくしは口から出まかせに吉原へ行くと言ったのであるが、行先の定(さだま)らない散歩の方向は、却(かえっ)てこれがために決定せられた。歩いて行く中(うち)わたくしは土手下の裏町に古本屋を一軒知っていることを思出した。
古本屋の店は、山谷堀(さんやぼり)の流が地下の暗渠(あんきょ)に接続するあたりから、大門前(おおもんまえ)日本堤橋(にほんづつみばし)のたもとへ出ようとする薄暗い裏通に在る。裏通は山谷堀の水に沿うた片側町で、対岸は石垣の上に立続く人家の背面に限られ、此方(こなた)は土管、地瓦(ちがわら)、川土、材木などの問屋が人家の間に稍(やや)広い店口を示しているが、堀の幅の狭くなるにつれて次第に貧気(まずしげ)な小家(こいえ)がちになって、夜は堀にかけられた正法寺橋(しょうほうじばし)、山谷橋(さんやばし)、地方橋(じかたばし)、髪洗橋(かみあらいばし)などいう橋の灯(ひ)がわずかに道を照すばかり。堀もつき橋もなくなると、人通りも共に途絶えてしまう。この辺で夜も割合におそくまで灯(あかり)をつけている家は、かの古本屋と煙草を売る荒物屋ぐらいのものであろう。
わたくしは古本屋の名は知らないが、店に積んである品物は大抵知っている。創刊当時の文芸倶楽部(クラブ)か古いやまと新聞の講談附録でもあれば、意外の掘出物だと思わなければならない。然しわたくしがわざわざ廻り道までして、この店をたずねるのは古本の為(ため)ではなく、古本を鬻(ひさ)ぐ亭主の人柄と、廓外(くるわそと)の裏町という情味との為である。
主人(あるじ)は頭を綺麗に剃(そ)った小柄の老人。年は無論六十を越している。その顔立、物腰、言葉使から着物の着様に至るまで、東京の下町生粋(きっすい)の風俗を、そのまま崩さずに残しているのが、わたくしの眼には稀覯(きこう)の古書よりも寧(むし)ろ尊くまた懐しく見える。震災のころまでは芝居や寄席(よせ)の楽屋に行くと一人や二人、こういう江戸下町の年寄に逢うことができた――たとえば音羽(おとわ)屋の男衆(おとこしゅ)の留爺(とめじい)やだの、高嶋屋の使っていた市蔵などいう年寄達であるが、今はいずれもあの世へ行ってしまった。
古本屋の亭主は、わたくしが店先の硝子(ガラス)戸をあける時には、いつでもきまって、中仕切(なかじきり)の障子際(ぎわ)にきちんと坐り、円い背を少し斜に外の方へ向け、鼻の先へ落ちかかる眼鏡をたよりに、何か読んでいる。わたくしの来る時間も大抵夜の七八時ときまっているが、その度毎に見る老人(としより)の坐り場所も其の形も殆どきまっている。戸の明く音に、折かがんだまま、首だけひょいと此方(こなた)へ向け、「おや、入らっしゃいまし。」と眼鏡をはずし、中腰になって坐布団の塵(ちり)をぽんと叩(たた)き、匐(は)うような腰付で、それを敷きのべながら、さて丁寧に挨拶をする。其言葉も様子もまた型通りに変りがない。
「相変らず何も御在(ござい)ません。お目にかけるようなものは。そうそうたしか芳譚(ほうたん)雑誌がありました。揃(そろ)っちゃ居りませんが。」
「為永春江(ためながしゅんこう)の雑誌だろう。」
「へえ。初号がついて居りますから、まアお目にかけられます。おや、どこへ置いたかな。」と壁際に積重ねた古本の間から合本(がっぽん)五六冊を取出し、両手でぱたぱた塵をはたいて差出すのを、わたくしは受取って、
「明治十二年御届としてあるね。この時分の雑誌をよむと、生命(いのち)が延(のび)るような気がするね。魯(ろ)文珍報も全部揃ったのがあったら欲しいと思っているんだが。」
「時々出るにゃ出ますが、大抵ばらばらで御在ましてな。檀那、花月新誌はお持合せでいらっしゃいますか。」
「持っています。」
硝子戸の明く音がしたので、わたくしは亭主と共に見返ると、これも六十あまり。頬のこけた禿頭(はげあたま)の貧相な男が汚れた縞(しま)の風呂敷包を店先に並べた古本の上へ卸しながら、
「つくづく自動車はいやだ。今日はすんでの事に殺されるところさ。
おぼろ気な記憶をたどれば、明治三十年頃でもあろう。神田錦町(にしきちょう)に在った貸席錦輝館で、サンフランシスコ市街の光景を写したものを見たことがあった。活動写真という言葉のできたのも恐らくはその時分からであろう。それから四十余年を過ぎた今日(こんにち)では、活動という語(ことば)は既にすたれて他のものに代(かえ)られているらしいが、初めて耳にしたものの方が口馴れて言いやすいから、わたくしは依然としてむかしの廃語をここに用いる。
震災の後(のち)、わたくしの家に遊びに来た青年作家の一人が、時勢におくれるからと言って、無理やりにわたくしを赤坂溜池(ためいけ)の活動小屋に連れて行ったことがある。何でも其(その)頃非常に評判の好いものであったというが、見ればモオパッサンの短篇小説を脚色したものであったので、わたくしはあれなら写真を看るにも及ばない。原作をよめばいい。その方がもっと面白いと言ったことがあった。
然し活動写真は老弱(ろうにゃく)の別(わかち)なく、今の人の喜んでこれを見て、日常の話柄(わへい)にしているものであるから、せめてわたくしも、人が何の話をしているのかと云うくらいの事は分るようにして置きたいと思って、活動小屋の前を通りかかる時には看板の画と名題とには勉(つと)めて目を向けるように心がけている。看板を一瞥(べつ)すれば写真を見ずとも脚色の梗概も想像がつくし、どういう場面が喜ばれているかと云う事も会得せられる。
活動写真の看板を一度に最(もっとも)多く一瞥する事のできるのは浅草公園である。ここへ来ればあらゆる種類のものを一ト目に眺めて、おのずから其巧拙をも比較することができる。わたくしは下谷(したや)浅草の方面へ出掛ける時には必ず思出して公園に入り杖(つえ)を池の縁(ふち)に曳(ひ)く。
夕風も追々寒くなくなって来た或日のことである。一軒々々入口の看板を見尽して公園のはずれから千束町(せんぞくまち)へ出たので。右の方は言問橋(ことといばし)左の方は入谷町(いりやまち)、いずれの方へ行こうかと思案しながら歩いて行くと、四十前後の古洋服を着た男がいきなり横合から現れ出て、
「檀那(だんな)、御紹介しましょう。いかがです。」と言う。
「イヤありがとう。」と云って、わたくしは少し歩調を早めると、
「絶好のチャンスですぜ。猟奇的ですぜ。檀那。」と云って尾(つ)いて来る。
「いらない。吉原へ行くんだ。」
ぽん引(びき)と云うのか、源氏というのかよく知らぬが、とにかく怪し気な勧誘者を追払うために、わたくしは口から出まかせに吉原へ行くと言ったのであるが、行先の定(さだま)らない散歩の方向は、却(かえっ)てこれがために決定せられた。歩いて行く中(うち)わたくしは土手下の裏町に古本屋を一軒知っていることを思出した。
古本屋の店は、山谷堀(さんやぼり)の流が地下の暗渠(あんきょ)に接続するあたりから、大門前(おおもんまえ)日本堤橋(にほんづつみばし)のたもとへ出ようとする薄暗い裏通に在る。裏通は山谷堀の水に沿うた片側町で、対岸は石垣の上に立続く人家の背面に限られ、此方(こなた)は土管、地瓦(ちがわら)、川土、材木などの問屋が人家の間に稍(やや)広い店口を示しているが、堀の幅の狭くなるにつれて次第に貧気(まずしげ)な小家(こいえ)がちになって、夜は堀にかけられた正法寺橋(しょうほうじばし)、山谷橋(さんやばし)、地方橋(じかたばし)、髪洗橋(かみあらいばし)などいう橋の灯(ひ)がわずかに道を照すばかり。堀もつき橋もなくなると、人通りも共に途絶えてしまう。この辺で夜も割合におそくまで灯(あかり)をつけている家は、かの古本屋と煙草を売る荒物屋ぐらいのものであろう。
わたくしは古本屋の名は知らないが、店に積んである品物は大抵知っている。創刊当時の文芸倶楽部(クラブ)か古いやまと新聞の講談附録でもあれば、意外の掘出物だと思わなければならない。然しわたくしがわざわざ廻り道までして、この店をたずねるのは古本の為(ため)ではなく、古本を鬻(ひさ)ぐ亭主の人柄と、廓外(くるわそと)の裏町という情味との為である。
主人(あるじ)は頭を綺麗に剃(そ)った小柄の老人。年は無論六十を越している。その顔立、物腰、言葉使から着物の着様に至るまで、東京の下町生粋(きっすい)の風俗を、そのまま崩さずに残しているのが、わたくしの眼には稀覯(きこう)の古書よりも寧(むし)ろ尊くまた懐しく見える。震災のころまでは芝居や寄席(よせ)の楽屋に行くと一人や二人、こういう江戸下町の年寄に逢うことができた――たとえば音羽(おとわ)屋の男衆(おとこしゅ)の留爺(とめじい)やだの、高嶋屋の使っていた市蔵などいう年寄達であるが、今はいずれもあの世へ行ってしまった。
古本屋の亭主は、わたくしが店先の硝子(ガラス)戸をあける時には、いつでもきまって、中仕切(なかじきり)の障子際(ぎわ)にきちんと坐り、円い背を少し斜に外の方へ向け、鼻の先へ落ちかかる眼鏡をたよりに、何か読んでいる。わたくしの来る時間も大抵夜の七八時ときまっているが、その度毎に見る老人(としより)の坐り場所も其の形も殆どきまっている。戸の明く音に、折かがんだまま、首だけひょいと此方(こなた)へ向け、「おや、入らっしゃいまし。」と眼鏡をはずし、中腰になって坐布団の塵(ちり)をぽんと叩(たた)き、匐(は)うような腰付で、それを敷きのべながら、さて丁寧に挨拶をする。其言葉も様子もまた型通りに変りがない。
「相変らず何も御在(ござい)ません。お目にかけるようなものは。そうそうたしか芳譚(ほうたん)雑誌がありました。揃(そろ)っちゃ居りませんが。」
「為永春江(ためながしゅんこう)の雑誌だろう。」
「へえ。初号がついて居りますから、まアお目にかけられます。おや、どこへ置いたかな。」と壁際に積重ねた古本の間から合本(がっぽん)五六冊を取出し、両手でぱたぱた塵をはたいて差出すのを、わたくしは受取って、
「明治十二年御届としてあるね。この時分の雑誌をよむと、生命(いのち)が延(のび)るような気がするね。魯(ろ)文珍報も全部揃ったのがあったら欲しいと思っているんだが。」
「時々出るにゃ出ますが、大抵ばらばらで御在ましてな。檀那、花月新誌はお持合せでいらっしゃいますか。」
「持っています。」
硝子戸の明く音がしたので、わたくしは亭主と共に見返ると、これも六十あまり。頬のこけた禿頭(はげあたま)の貧相な男が汚れた縞(しま)の風呂敷包を店先に並べた古本の上へ卸しながら、
「つくづく自動車はいやだ。今日はすんでの事に殺されるところさ。
下载地址:
点击下载TXT
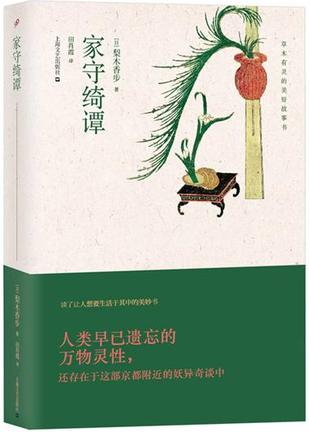 作者:永井荷风(日)
作者:永井荷风(日)